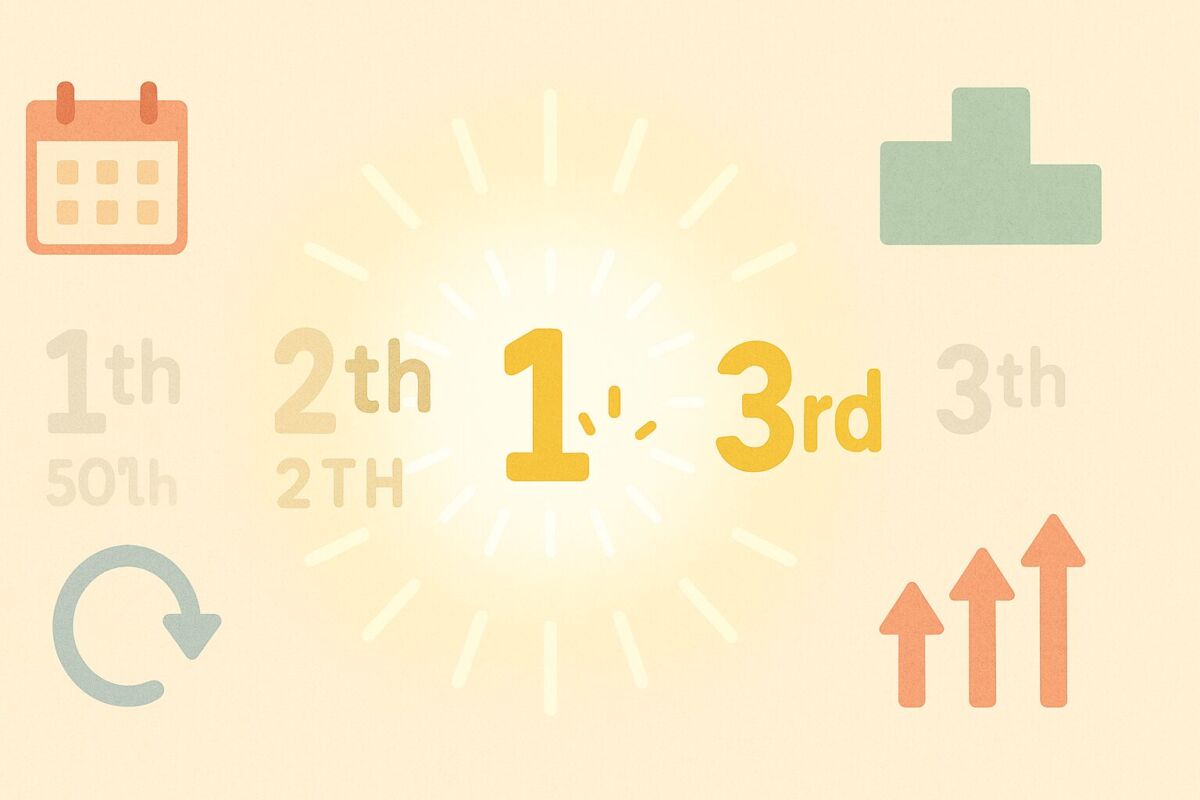英語の“順番の数字”がスッとわかる。今こそ序数のモヤモヤをゼロにしよう。
英語を学び始めると、「1」「2」「3」のような通常の数字だけでなく、「1st」「2nd」「3rd」という少し特別な表記に必ず出会います。
序数と呼ばれるこれらの表記は、順位や順番、位置を伝えるために日常的に使われます。
しかし、初心者が陥りやすいミスとして「1th」「2th」「3th」という誤った書き方も広く見られます。
本記事ではこれらの違いを、英語初心者でも迷わず理解できるように丁寧に解説します。
基数と序数の違い、読み方、使い方、よくある誤解、実際の会話・文章での注意点など、英語学習の基礎をしっかり固められる内容として6000字超の大ボリュームでまとめました。
前半では序数の基本と「1st/2nd/3rd」が特別扱いされる理由を中心にくわしく解説します。
序数とは何か

英語で順番や位置を説明するときに使われるのが「序数(ordinal numbers)」です。
序数は、単に順位を表すだけでなく、物の場所、段階、工程の流れなど、さまざまな“順序そのもの”を正確に伝えるための重要な表現です。
たとえば、スポーツ競技の結果発表、料理レシピの「手順1・手順2」、建物の階数、さらには誕生日を表す日付表記まで、日常生活のあらゆる場面に登場します。
英語に不慣れな初心者ほど、この序数の理解が曖昧なまま使い始めてしまうことが多く、結果として誤表記や誤発音につながるケースが少なくありません。
そのため、学習の早い段階で序数の成り立ちや使われ方を正しく押さえておくことは、英語理解の基礎力を大きく高める鍵となります。
また、序数は基数とは見た目も役割も異なるため、両者の違いをはっきり理解しておくことで、文脈ごとに自然な言い換えができるようになり、会話やライティングの幅が格段に広がります。
序数の代表例

1番目 → first(1st)
2番目 → second(2nd)
3番目 → third(3rd)
4番目以降 → fourth(4th)、fifth(5th)、sixth(6th)、seventh(7th)… と続きます。
これらの語彙は、学校のテスト、スポーツ大会の順位表、ニュースや天気予報の発表、アナウンス、SNS、ビジネス文書、メール、プレゼン資料、公式イベントの日程案内など、あらゆる場面で頻繁に使用されます。
特に日付の読み上げでは序数が必須となるため、英語圏で生活したり海外の情報に触れたりすると、序数の重要性を強く実感することになります。
「1st, 2nd, 3rd」はなぜ特別なのか

序数の中で最も混乱を生むのは「1, 2, 3」だけ語尾が違うという“特別扱い”です。
この3つだけが例外となる理由は、英語の古い言語変化に由来しており、もともとの語源が現在の形に強く影響しています。
つまり、first・second・third は【語尾にルールを付ける前から存在していた特別な語彙】であり、後から体系化された「th で統一する」という仕組みの外側にある単語なのです。
そのため、英語では「1→st」「2→nd」「3→rd」が長い歴史の中で慣習化し、そのまま現代英語にも引き継がれています。
英語の初心者は「th を付ければ序数になる」と単純化して覚えてしまいがちですが、実際には語源・語彙の歴史が深く関係しているため、この3つだけが特別な扱いを受けているのです。
さらに、これらの例外は日常生活のさまざまな場面で繰り返し使われ、英語ネイティブの感覚に深く根づいてきました。
そのため、ネイティブスピーカーは「1st・2nd・3rd」を見ると自然に正しい形として受け入れますが、「1th・2th・3th」を目にすると即座に違和感を覚えます。
この“違和感”は単なる形式的ミスにとどまらず、「英語の基礎が身についていない」という評価に直結することもあり、ビジネス・学術・試験などフォーマルな場面では特に厳しく見られます。
語尾の例外ルール
1 → st(first 由来)
2 → nd(second 由来)
3 → rd(third 由来)
4以降 → th(規則的に形成された語尾)
このルールを無視すると、「1th」「2th」「3th」といった誤表記になり、英語に慣れている人ほど強烈な違和感を覚えます。
とくに、英語圏の人々にとって序数は非常に基本的で頻繁に使われる知識のため、間違いが非常に目立つポイントでもあります。
そのため、学習者は早い段階でこの“3つだけの例外”を確実に覚えておくことが、正しい英語表現への近道となります。
「1th・2th・3th」が誤りである理由

英語学習者がつまずきやすい最大のポイントがこの誤表記です。 初心者だけでなく、中級者でもうっかり使ってしまうケースがあり、実は英語学習の長い過程の中でも繰り返し注意が必要なテーマです。
とくにSNSやカジュアルなチャットでは誤って使われている例も多いため、「間違っていても伝わるかもしれない」「カジュアルなら問題ないだろう」と誤解する人もいます。
しかし、こうした誤った認識が身についてしまうと、フォーマルな英語を書く場面で大きなミスにつながり、読み手に強烈な違和感を与える可能性があります。
また、SNS上で誤表記を真似して学習してしまう人も多く、ネット上での“誤学習連鎖”が起こりやすい点も見逃せません。
英語の基礎が固まっていない状態ほど、誤った用法を長期間使ってしまいやすく、その後に修正するにも苦労するケースが多く見られます。
このため、序数の正しいルールを早い段階で確実に身につけ、どのような場面でも自信を持って使えるようにしておくことがとても重要です。
さらに、この誤表記は単なるスペルの間違いに留まらず、読み手とのコミュニケーション精度にも影響します。
たとえば「1th day」と書いてしまうと、「1日目」なのかどうなのか判別できず、日程調整や予定確認で混乱を招くこともあります。
誤表記は読み手の理解を妨げ、ビジネスや学習環境では信頼低下につながりかねません。
そのため、こうした小さなミスこそ丁寧に直し、表記ルールを理解したうえで使う習慣を身につけることが重要です。
間違いの主な原因
- 「thを付ければすべて序数になる」と誤解している
- 1・2・3に特別な語尾があることを知らない
- 教科書よりもネットで誤表記に触れる機会が多い
- スペル暗記の段階で混同してしまう
- そもそも序数と基数の役割の違いがあいまいなまま学習している
- 英語の語源知識が不足しており「例外」が頭に入りにくい
正しい知識を身につけておくことは、日付や順位、ビジネス文書などで誤った印象を与えないだけでなく、文章全体の信頼性を高めるうえでも非常に大切です。
相手に伝わりやすい英文を書くためにも、序数の正しい表記・発音・使い分けを身につけることが、英語学習の大きな基盤となります。
基数(cardinal numbers)との違い
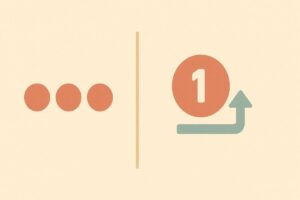
英語の数字には大きく分けて「基数(数そのもの)」と「序数(順番)」があります。
この2つはどちらも数字を扱う表現ですが、役割も意味もまったく異なります。
その違いを理解することは、正確で自然な英語表現を身につけるうえで非常に重要です。
英語初心者は、この違いを曖昧なまま学習を進めてしまうことが多く、結果として誤用を繰り返したり、相手に伝わりにくい英文になってしまったりします。
特に、数量と順番の混同は、会話の誤解・メールの読み違い・文書の不備につながりやすく、学習段階だけではなく実務でも問題になり得ます。
基数と序数の違いを正しく押さえることで、英語での説明能力が大きく向上し、会話・SNS・ビジネス文書のいずれでも自信を持って表現できるようになります。
さらに、両者の違いを意識的に使い分けることで、学術論文の引用番号、表やグラフの説明、旅行の日程案内など、より複雑な英語にも対応できるようになります。
基数とは
基数は「いくつあるか」を表す数字です。
1 → one
2 → two
3 → three
基数は数量そのものを表すため、日常生活のあらゆる場面で登場します。
買い物、食材の数、人数、物の個数、単純な数え上げなど、英語でもっとも頻繁に使う数字の基本形です。
学び始めたばかりの段階では基数の暗記から始まりますが、その背景には「数そのものを表現できる」重要な役割があります。
例:I have three apples.(私はリンゴを3つ持っています)
この例文が示すのは“リンゴの数がいくつあるか”という情報のみで、そこに順番の概念はありません。
数量を正確に伝えたい場合、必ず基数を使う必要があります。
序数とは
序数は「何番目か」を表す数字です。
1st → first
2nd → second
3rd → third
序数は数量とは異なり、「位置」「順序」「並びの中での順位」を示す表現です。
スポーツ順位、料理手順、説明ステップ、部屋番号、日付、建物の階数など、順序が意味を持つ場面では必ず序数が使われます。
英語ネイティブにとっても、序数は非常に基本的な語彙であり、読み間違いや書き間違いをすると一気に不自然な印象を与えるほど重要なカテゴリーです。
例:This is the third apple.(これは3番目のリンゴです)
この文は数量ではなく“位置”を表しており、基数(three)とは異なる意味を提供しています。
基数と序数の使い分け例
同じ数字でも、文脈によって意味が大きく変わります。
この違いは英語学習において特に重要で、基数と序数を取り違えると、相手に誤った情報を伝えてしまう可能性があります。
たとえば、数量を言いたいのに序数を使ってしまうと「3つ」ではなく「3番目」と意味が変わってしまい、指示や説明が正しく伝わらない原因になります。
逆に、順番を示すべき場面で基数を使ってしまうと、「どの位置なのか」が曖昧になり、文脈の理解を妨げてしまいます。
そのため、両者の違いを感覚的に理解し、場面ごとに自然に使い分けられるようになることが、英語での正確なコミュニケーションにつながります。
具体例
- 数量の「3つ」 → three
- 順番の「3番目」 → third
- 3回実施する → three times(回数)
- 3回目の実施 → the third time(順序)
このように、同じ「3」でもニュアンスがまったく異なるため、英語では頻繁に基数と序数が使い分けられています。
特に「回数」と「順番」の違いは誤解を生みやすいため、学習者は重点的に意識する必要があります。
また、スポーツ、日付、建物の階数など、序数は生活のあらゆる場面で必要になります。
順位の発表、誕生日の説明、予定の確認、部屋番号の案内、ステップ式の説明など、序数を使う機会は非常に多く、英語を使う以上避けられない重要な領域です。
序数の理解が深まるほど、自然で正確な英語表現ができるようになります。
序数の読み方と発音のポイント

序数は書き方だけでなく「読み方」も基数とは大きく異なります。
英語では、単語の意味だけでなく“どう発音するか”も重要であり、特に序数は発音が基数とは大きく変わるため、初学者にとって大きなつまずきポイントになることがあります。
間違った読み方をすると、ネイティブにはすぐに不自然な印象を与えてしまうため注意が必要です。
さらに、序数の単語はフォーマルな場面やプレゼン、学校のテスト、アナウンス、日付の読み上げなど重要な場面で多用されるため、誤った発音は内容理解の妨げになったり、話し手としての信頼を損なったりする原因にもなります。
代表的な読み方
1st → first(ファースト)
2nd → second(セカンド)
3rd → third(サード)
4th → fourth(フォース)
5th → fifth(フィフス)
ここで特に難しいのが、英語特有の“th”の発音です。
日本語には存在しない音であるため、多くの学習者が「サード」を「サードゥ」「サードス」など不自然な音で発音してしまう傾向があります。
「third」の“th”の発音は、日本語にないため練習が必要です。
舌を軽く歯に当てて息を出すイメージで発音します。
その際、舌を強く噛まないようにしながら、息を前に吹き出すように意識すると、より自然な発音に近づけます。
また、序数の発音はストレス(強勢)の位置によってニュアンスが変わることもあり、英語音声を繰り返し聞きながら発音練習することが効果的です。
オンライン辞書、英語学習アプリ、YouTube の発音解説、英語教材の音声などを活用すると、より正確な発音を身につけやすくなります。
序数の発音をマスターすると、日付の読み上げや順位説明、ステップの指示など、英語を使うあらゆる場面で表現力が大きく向上します。
誤った読み方が引き起こす誤解
たとえばプレゼンで「1th」を「ワンス」と読んでしまう、または文字通り「ワンス-th」のように誤って言ってしまうと、文章内容よりミスが目立ってしまいます。
さらに悪いことに、こうした誤った読み方は聞き手の集中をそらし、話し手が伝えたかった本来のメッセージよりも“ミスそのもの”が印象として強く残ってしまいます。
特にプレゼンテーションや面接、商談など、慎重さと正確さが求められる場面では、こうした小さな発音ミスが「準備不足」「基礎が身についていない」という否定的な評価に直結する可能性があります。
また、会議の議事録作成やスケジュールの読み上げなど、正確な情報伝達が求められる状況では、誤った発音により日付や手順の解釈がズレる危険も伴います。
とくにビジネスの場面では信頼性が下がる原因にもなり、正しい序数の習得は必須です。
誤発音を避けることで、プロフェッショナルとしての印象を大きく向上させ、聞き手に安心感と信頼感を与えることができます。
正しい序数表記のルール(数字)

序数を数字で書くときには、語尾を正しく付ける必要があります。
その語尾のルールを正しく理解することで、日付の書き方、順位の表示、学術的な文献番号、プレゼン資料のスライド順番の記載など、実に幅広い場面で迷わなくなります。
とくに英語圏では、数字と語尾の組み合わせは非常に厳密に扱われる傾向があり、誤った語尾を付けてしまうと「読み手に即座に違和感を与える」「フォーマル文書として不適切と判断される」などの問題を招く可能性があります。
以下では、序数の基本的な一覧をさらに丁寧に紹介しながら、それぞれの使い方やシーンも補足していきます。
序数の表記一覧(1〜10)
1 → 1st(イベントの「1日目」、レースの「1位」などでよく使用)
2 → 2nd(2回目の訪問、2章、2段階目などの表現に用いられる)
3 → 3rd(3番目の手順、3位の順位など)
4 → 4th(英語では “fourth” のスペルに注意が必要)
5 → 5th(fifth は f が二重になる点が学習者のつまずきポイント)
6 → 6th(sixth は発音がやや難しく、聞き取りでも注意)
7 → 7th(seventh の語尾 -enth と関連し覚えやすい)
8 → 8th(eight に th が付くためスペルミスに注意)
9 → 9th(ninth は語尾が短く変化する点に注意)
10 → 10th(tenth は日常会話でも頻繁に登場)
これら 1〜10 の序数は、英語のあらゆる場面で基礎中の基礎として使われ、特に日付の読み上げではほぼ必須になります。
たとえば “March 3rd(3月3日)” や “July 1st(7月1日)” といった形で使われるため、英語圏のカレンダーを読む際にも重要な知識となります。
2桁以上の序数(下1桁のルール)
英語の序数は、2桁以上の数字でも「下1桁」に注目して語尾を決めるというルールがあります。
21 → 21st(下1桁が 1 なので st)
22 → 22nd(下1桁が 2 なので nd)
23 → 23rd(下1桁が 3 なので rd)
24 → 24th(4 以降はすべて th)
この原則は 31st、42nd、113th のように、どれほど数字が大きくなっても変わりません。
そのため、1桁と同じパターンを覚えておけば、より大きな数字でも直感的に序数へ変換できるようになります。
ただし例外として、「11th」「12th」「13th」の 3つのみは、下1桁が 1・2・3 でも th を使用する点に注意が必要です。
これは歴史的・語源的な理由から定着したルールであり、英語学習者が最初に混乱しやすいポイントのひとつです。
(例:11th, 12th, 13th は all “th”)
この仕組みを理解しておくと、日付などの書き方で迷うことがなくなります。
さらに、英語でスケジュール調整をするとき、学術的な章番号を扱うとき、イベントの順番を説明するときなど、さまざまな場面で自信を持って正しい序数を使えるようになります。
序数の実践活用とよくある疑問
ここからは、序数が実際の英語運用の中でどのように使われるか、さらに深い理解と応用ができるように詳しく解説します。
このパートでは、序数が英語の実生活でどれほど頻繁に登場するか、またどんな文脈で使われるとより自然で正確な表現になるのかを、初心者でも理解しやすいように丁寧に紹介します。
序数は単に「順番を示すための数字」として覚えるだけでは不十分で、実際の会話・資料・メールなど具体的なシーンと結びつけて学習することで、一気に使いこなしやすくなります。
さらに、ここで扱う例は英語圏では“日常のごく当たり前の用法”であるため、それぞれの場面でどのように聞こえ、どんな伝わり方をするのかを意識しながら読むことで、より深い理解につながります。
日付での序数の使い方
英語の日付では、ほぼ例外なく序数が使われます。
これは英語圏における強固な文化的慣習であり、ネイティブにとって「日付=序数」で書くのが自然なため、誤った書き方はすぐに違和感として認識されます。
例:March 5th(3月5日)
例:July 21st(7月21日)
さらに、日付における序数は “spoken English(話し言葉)” と “written English(書き言葉)” の両方で必須となるため、旅行・留学・海外のニュース閲覧など、生活シーンでも多用されます。
また、「5日間滞在した」「21日に出発する」などの日程説明でも頻出するため、正しく習得しておくとスケジュール管理がぐっと楽になります。
建物の階数での序数
英語では階数も序数で表します。
例:I live on the third floor.(3階)
序数を使う理由は、日本語とは異なり英語では「階」は“数字そのもの”ではなく“位置”を示す概念として扱われるためです。
そのため基数(three)ではなく序数(third)が使われ、ホテル・マンション・オフィスビルなど、建物の案内では例外なく序数が登場します。
また、イギリス英語とアメリカ英語では階数表記が異なる(例:日本の1階=アメリカの1st floor、イギリスの ground floor)ため、海外滞在時には序数の理解が特に役立ちます。
プレゼン資料や章番号
スライド番号や章番号も序数が使われます。
例:This is the 2nd chapter.(第2章)
ビジネス資料、研究レポート、書籍の目次、講義資料などでは、章立てやステップ構造を明確に示すために序数が適切に用いられます。
特に “the first step”“the second section”“the third slide” のような使い方は、論理展開をスムーズに伝えるうえで非常に重要です。
さらに、国際会議や学会発表などフォーマルな場面では、序数の誤りが即座に質の低さとして判断されてしまうため、正確な使い方を身につけることが求められます。
序数に関するよくある誤解
11th, 12th, 13th が例外な理由
下1桁が 1・2・3 でも、11・12・13 は語尾が “th” になります。
これは歴史的に “eleventh”“twelfth”“thirteenth” が規則的に th を取るためで、英語の語源に基づいた例外です。
さらに詳しく説明すると、この 11〜13 に関する特殊ルールは、古英語(Old English)の語形変化に起源があります。
英語では long time ago、数字 1・2・3 に対応する語が、ほかの序数とは異なる独自の変化を伴っていました。
特に “eleventh” と “twelfth” は、他の序数には見られない語彙的変化(suppletion)が含まれており、語尾を単純に一致させるのではなく、語全体が独自に変化して発展した歴史があります。
さらに、13 の “thirteenth” に関しても、three → third のように特有の変化があるため、語尾だけを単純に置き換えるルールでは対応しきれず、自然と “th” が定着したとされています。
そのため、見た目だけでは「23rd と同じく 13rd と書くべきでは?」と思いがちですが、英語の語源・歴史的発展の流れを辿ると、11〜13 が 特別扱い となっている理由が明確に理解できます。
また、11th・12th・13th は英語ネイティブにとっても“特別な塊”として認識されており、日常会話でも書き言葉でも自然に th が使われます。
そのため、学習者が 11st・12nd・13rd と書いてしまうと、ネイティブには非常に不自然に見え、“教科書レベルの基礎が理解できていない”という強い印象を与えてしまうことがあります。
この 11〜13 の例外ルールは序数の基礎の中でも特につまずきやすいポイントですが、一度理解してしまえば応用範囲が非常に広く、正しい表記が直感的に選べるようになります。
th の発音が苦手な人へ
th の発音が難しい場合、まずは無理に英語らしく発音しようとせず、舌を軽く前歯に当てて息を出す練習から始めるとスムーズに上達します。
この“舌を歯に当てて息を出す”という動作は非常にシンプルですが、英語学習者にとってもっともつまずきやすい発音のひとつです。
というのも、日本語ではこの位置に舌を置いて息を出す音が存在しないため、身体的に慣れておらず、最初は違和感を覚えやすいからです。
また、ネイティブの th の発音は「舌を強く噛む」のではなく「そっと前歯に触れさせながら軽く息を前に流す」イメージで行われます。
この“軽さ”が再現できると、一気に自然な音に近づきます。
さらに練習効果を高めるには、鏡を使いながら舌の位置を確認したり、スマホで録音して自分の発音を客観的に聞いたりする方法が効果的です。
慣れてきたら、短い単語(think, thank, three など)をゆっくり発音し、徐々にスピードを上げていくとスムーズに習得できます。
加えて、発音練習アプリやオンライン辞書の音声と比較することで、ネイティブの息の出し方・舌の動きを視覚的に確認できるため、より高い効果が得られます。
th の発音は難しいと感じる学習者が多い一方で、コツを押さえれば確実に上達する発音でもあります。
焦らず段階的に練習を進め、まずは“音をまねる”より“口の形と息の流れを習慣化する”ことを意識すると、驚くほど自然な th が発音できるようになります。
英語学習で序数をマスターするメリット
文章の正確さが大幅に向上する
序数は英語の基礎の中でも“正確さ”を支える重要なパーツです。
単なる数字の置き換えのように見えますが、実際には文章全体の意味理解やニュアンスに大きな影響を与える非常に繊細な要素です。
序数が正確に使われているだけで、読み手は「この文章は丁寧に書かれている」「基本がしっかりしている」という印象を自然と受け取ります。
特に英語では、数字まわりの間違いが意味の取り違いに直結しやすいため、1つの小さなミスが文章全体の信頼性に大きく影響します。
たとえば「the 3rd step(3番目の手順)」と「the three steps(3つの手順)」を誤って使うと、読み手が理解できる情報そのものが変わってしまいます。
さらに、序数を正しく使うことで冗長な説明を避け、スッキリと読みやすい英文に整えることができます。
結果として、メール・資料・会話の印象が一段上がり、読み手の理解速度も早くなるため、コミュニケーションの質を大きく向上させる効果があります。
ビジネス英語での信頼度アップ
日付、段階、優先順位など、ビジネスでは序数の使用頻度が非常に高く、的確に使えるとプロフェッショナルな印象を与えます。
さらに、ビジネス英語では数字の扱いが極めて重要であり、日程調整・プロジェクト管理・資料作成・スケジュール報告など、ほぼすべての場面で序数が登場します。
「our 2nd meeting」「the 5th version of the report」「the 1st phase of the project」など、序数は専門性と正確性の象徴とも言える表現です。
こうした部分を正しく書けるだけで、相手から見たときの信頼度は大きく跳ね上がります。
逆に「1th meeting」「3th step」のような誤表記があると、英語の能力に疑問を持たれたり、資料そのものの信頼性が低く見られたりする可能性があります。
ビジネスでは細部の正確性が非常に重視されるため、序数を正しく扱えることは、実務能力や注意深さを示す1つの重要な指標にもなるのです。
学習効率の向上
序数を理解すると、英語の構造的ルールがより明確に把握でき、他の文法事項の習得スピードも上がります。
序数には語尾変化、例外ルール、語源的背景など複数の学習要素が含まれており、これらを整理して理解することで英語全体の“規則性”と“例外”の感覚が身につきます。
また、基数との違いを明確に意識できるようになることで、日付・手順・順位などの説明をスムーズに行えるようになり、英語の読み取り・会話・文章作成の精度が高まります。
序数を学ぶことは、単なる暗記ではなく英語の構造理解を深める一歩であり、学習全体の効率向上にもつながります。
序数を理解すると、英語の構造的ルールがより明確に理解でき、他の文法事項の習得スピードも上がります。
まとめ

小さな語尾が、大きな英語力の差になる。
序数を味方にすれば、あなたの英語はもっと伝わる。
序数は英語の基礎にして応用範囲の広い、非常に重要なカテゴリーです。
序数は単に「順番を示す数字」という枠を超え、英語の文章構造・説明能力・情報整理の正確性を支える“言語の土台”として大きな役割を果たしています。
特に日常会話・ビジネス文書・学術資料・旅行会話など、あらゆる場面で頻繁に登場するため、序数を正しく理解しておくことは英語運用能力を支える基盤となります。
初心者が序数を確実に身につけることで、英語の文章を読む際の理解スピードが大きく上がり、会話でも自然なフレーズが使えるようになり、自信を持って英語を扱えるようになります。
「1st・2nd・3rd」が例外であり、それ以外が「th」を取るという基本ルールを押さえるだけで、英語表現の正確さが大きく向上します。
このルールを理解しておくと、文章の意味を取り違えたり、読み手に誤解を与えたりする可能性が大幅に減り、フォーマルな英語でも安心して使えるようになります。
さらに、序数の正しい知識はメールのスケジュール調整、アポイントの管理、レポート作成、数字の読み上げなど、実務的な場面でも大きな力を発揮します。
日付・順位・階数・手順など序数が活躍する場面は非常に多いため、早い段階での習得が英語力向上につながります。
また、序数を意識的に使い分ける習慣を身につけることで、論理的で誤解のない英文が書けるようになり、日常からビジネスまで幅広い場面での英語運用能力が強化されます。
FAQ
Q1:11st や 12nd は間違い?
はい、すべて誤りです。11・12・13 は語尾がすべて “th” になります(11th, 12th, 13th)。
これらの 11〜13 が例外になる理由は、単純な語尾の規則では説明できず、英語の語源や歴史的な変化に深く関係しています。
数字の 1・2・3 が単独で使われる場合には特別な語尾(st / nd / rd)が付くにもかかわらず、11・12・13 のときに “th” を取るのは、それらの語が古英語期から独自に変化してきたためです。
特に “eleventh” “twelfth” “thirteenth” という語形は、他の序数とは異なる発展をしてきた語彙であり、語尾が統一される前から「独立した単語」として存在していました。
そのため、21st・42nd・103rd のように規則に従って語尾を変化させる通常の序数とは異なり、11〜13 だけは語尾を“th”で固定したまま現在まで定着しています。
英語ネイティブにとっても、11th・12th・13th は“自然で当然の形”として認識されているため、11st や 12nd のような誤表記を見るとすぐに不自然さを感じるのが一般的です。
この例外ルールは序数学習の重要ポイントであり、正しく理解しておくと日付・順位・資料番号などを扱う場面で迷わなくなります。
Q2:序数は話すとき省略できる?
読みにくい場合も、省略はできません。読み方は first, second, third などの単語として必ず発音します。
序数は数字に語尾を付けただけの“記号”ではなく、英語では独立した“単語”として扱われるため、発音を省略することはできません。
英語ネイティブも、数字部分を読むのではなく「first」「second」「third」のように、序数そのものを単語として発音します。
たとえば “June 3rd” は “June third” と読み、“June three” とは発音しません。
読み方を省略してしまうと意味が変わったり、不自然に聞こえたりするため、フォーマル・カジュアルを問わず正確に発音する必要があります。
また、プレゼンやアナウンスなど聞き手の理解が重要な場面では、序数の正確な発音が情報伝達の精度を大きく左右します。
Q3:th の発音が難しいときは?
舌を軽く歯に当て、息を前に押し出すように発音する練習を繰り返すと上達します。
“th” の発音は日本語に存在しないため、多くの学習者が苦手意識を持つ部分ですが、正しい舌の位置を知れば確実に上達できます。
まずは鏡を使い、舌先が上下の前歯の間にほんの少しだけ覗くように出す形を確認しましょう。
このとき舌を噛んでしまう必要はなく、軽く触れるだけで十分です。
次に、息をスッと前に流す意識で “th” の母音なしの音を作り、その後で “thirty”“third”“thanks” のような実際の単語で練習します。
音声教材や辞書アプリのネイティブ発音を真似し、自分の声を録音して比較すると、舌の位置や息の強さの改善点がわかりやすくなります。
練習を繰り返すことで、日付や順位を読む際にも自然な発音ができるようになり、聞き手に伝わりやすい英語になります。